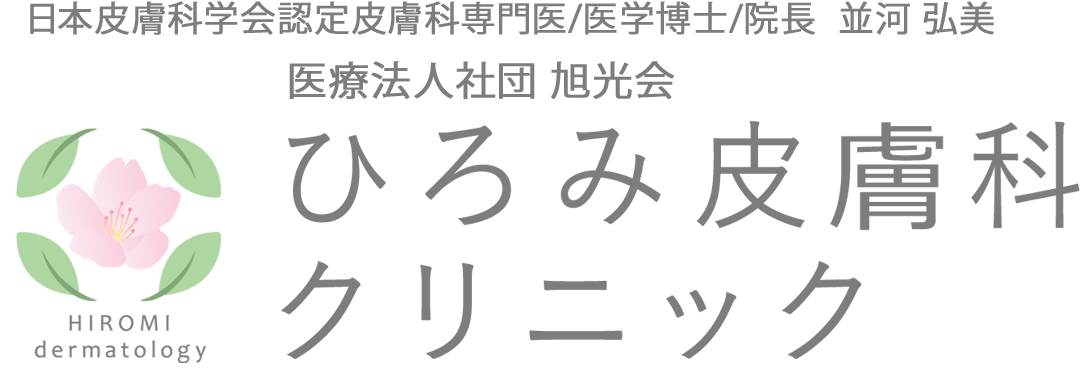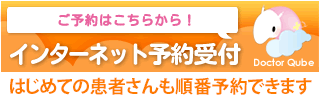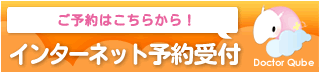医療機関情報
| 医院名 | 医療法人社団 旭光会 ひろみ皮膚科クリニック |
|---|---|
| 院 長 | 並河 弘美 |
| 住 所 | 東京都練馬区東大泉4-29-39 大泉中学校すぐ近く |
| 診療科目 | 皮膚科・小児皮膚科・アレルギー科・美容皮膚科 |
| 電話番号 | 03-3925-2606 |
| 治療機器 | ナローバンドUVB、イオントフォレーシス |

WEB予約受付サイト QRコード
小児皮膚科について
お子様のお肌は大人に比べてとてもデリケートです。またお子様特有の皮膚症状も少なくありません。自分の症状を言葉で伝えられないことが多く、気が付いた時には悪化してしまっているケースもあります。お子様の皮膚の症状の変化に気がつかれましたら早めに相談にいらして下さい。
お子様の主な皮膚疾患について
代表的な小児皮膚症状について
とびひ
とびひには水ぶくれができるもの(水疱性膿痂疹)とかさぶたができるもの(痂皮性膿痂疹)の2種類があります。皮膚にできた水ぶくれが、だんだん膿をもつようになり、やがて破れると、皮膚がめくれてただれてしまいます。痒みがあり、そこを掻いた手でほかの場所を触ると、症状が体のあちこちに広がってしまいます。とびひの多くはこのタイプで、主な原因は黄色ブドウ球菌です。
痂皮性膿痂疹は皮膚の一部に膿をもった水ぶくれ(膿疱)が生じ、厚いかさぶたになります。炎症が強く、リンパ節が腫れたり、発熱やのどの痛みを伴ったりすることもあります。主に化膿レンサ球菌が原因となりますが、黄色ブドウ球菌も同時に感染しているケースが少なくありません。
原因は湿疹、虫刺され、あせも、擦り傷などのところを引っかいたりする事により、ブドウ球菌や溶血性レンサ球菌などが侵入し、感染をおこします。
細菌を抑える抗生剤を飲みます。かくことによってとびひが増えるのを防ぐため、かゆみ止めを飲む場合もあります。また塗り薬はシャワー後に水分をよくふきとって、抗生剤またはステロイド含有の抗生剤を塗ります。
水いぼ
水いぼは伝染性軟属腫と言われ、伝染性軟属腫ウイルスに感染することで起こる皮膚のいぼです。基本的には子どもの病気ですが、大人でもまれに感染することがあります。
原因は水いぼにかかっている子供のいぼに直接触れたり、同じタオルを使ったり、ビート板や浮き輪、ウイルスの付いた遊具などに触れたりして感染すると言われています。
水いぼを放置しても自然に治りますが、6か月から5年と長い期間がかかります。その間にほかの場所に増えてしまったり、他の人にうつしたりすることがありますので、水いぼの数が少ないうちに取っておいた方が良いといわれています。
手足口病
手足口病とは、口の中や、手足などに水疱性の発疹が出るウィルス感染症です。子どもを中心に、主に夏季に流行します。コクサッキーウイルスやエンテロウイルスなどの感染によって起こります。感染経路としては、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)などが知られています。特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは集団感染が起こりやすいため、注意が必要です。
症状としては、感染してから3〜5日後に、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2〜3mmの水疱性発疹が出ます。発熱は約3分の1に見られますが、高熱になることは少ないです。多くは、数日のうちに治ります。ウィルス感染症のため髄膜炎や脳炎の注意は必要です。
りんご病
りんご病の正式名称は伝染性紅斑といいます。両ほおに紅斑が生じることを特徴とし、幼児・学童に多い急性ウイルス性疾患です。ほっぺが、りんごのように赤くなることから、よくりんご病と呼ばれます。
りんご病の原因は、ヒトパルボウィルスB19というウィルスです。学童期(6〜12歳)にかかることが多く、冬から春にかけて、保育施設や学校で流行します。接触・飛沫感染すると考えられていますが、発疹が現れた時には、もう伝染力は無いと言われます。
症状としては、はじめに風邪のような症状(発熱、筋肉痛、倦怠感)が出て、しばらくすると両ほおが赤くなり、その後、腕や太ももに発疹ができます。発疹は、はじめはポチポチとした斑点のようですが、次第に中央部が退色し薄くなり、まわりを赤く縁取ったレース模様のようになるのが特徴です。
頭じらみ
あたまじらみは主に頭髪に寄生して頭皮から吸血する昆虫で、体長は2~4mm大です。
主に頭髪の直接的な接触により感染します。幼稚園児や学童などの間で流行し、その家族にも感染します。症状は卵が毛髪に多数付着しかゆみが出る場合が多いです。卵や虫体を確認すれば診断が確定します。
おむつかぶれ
おむつ部に生じる皮膚に起きた炎症で医学的にはおむつ皮膚炎といいます。炎症はかゆみを伴って悪化するとただれて血がにじむ赤ちゃんもいます。おむつ自体の摩擦や尿や便による刺激などが原因となります。ステロイド外用により治療されることが多いですが、かびによる皮膚炎を合併したときはステロイドの塗り薬では治りません。鑑別するには顕微鏡で検査し、診断して加療致します。
あせも
汗の腺の閉塞により汗が排出されずに貯留することにより生じる発疹の総称で、貯留する深さにより水晶様汗疹、紅色汗疹、深在性汗疹に分類されます。乳幼児では温熱に対して発汗作用が過敏で発汗しやすいため、発汗をさけ風通しをよくし涼しい環境作りや発汗後のシャワーが重要です。場合によりステロイドの外用にて加療致します。